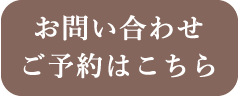脾
こんにちは。
西荻院の長谷部です。
本日はタイトルにある「脾」についてお話させていただきます。
東洋医学で「脾」とは「胃腸」のことを表します。
そしてこの「脾」は身体にとってとても大切な働きをしています。
その働きとは、食物を消化・吸収し全身に栄養を運ぶことです。
そしてこの「脾」の特徴の一つに、「脾は湿を嫌う」というのがあります。
これは「脾」は湿気が苦手で、過剰になると働きが弱まるということを表しています。
湿気が過剰になる要因としては、外的なものと内的なものに分けられます。
外的な要因とは主に自然環境で、雨や曇天、梅雨時期などが特に当てはまります。こういった湿度が高い環境にいると体内の湿気も溜まりやすくなります。
内的な要因としては主に食事の内容で、生もの、甘いもの、脂っこいもの冷たいものなどは湿が豊富で、こういったものの摂取が増えてくると体内に湿が溜まってしまいます。
この外と内の二つの要因…
そう、日本はこの要因がよく当てはまる国なんです。
もともと多湿な気候で、生もの(お寿司やお刺身、生野菜など)もよく食べる文化です。
そのため、身体の湿は溜まりやすく、その結果「脾」の働きが弱まってしまいます。
「脾」の働きが弱まることで、からだに必要な栄養素を吸収できずエネルギー不足になったり、からだに不必要なものが溜まってしまい、なかなか疲れが抜けなかったり、からだが重く感じたりなどはじめはなんとなく調子が悪く感じるようになります。
その状態がさらに進んでいくとだんだんお腹が張ったり、お腹を下しやすくなるなどお腹自体の不調も感じるようになり、そこからからだの様々な不調に繋がっていってしまいます。
上記の症状に自覚がある方は、消化に悪い食事(生ものや甘いものや油ものなど)を控えたり、水分の摂りすぎには注意が必要です。
また湿の排泄を促すような食材を適度に摂っていただき、身体に溜まった余計な水分を排出して頂くのも有効です。
湿の排泄を促す食材
豆類、白菜、アスパラガス、セロリ、とうもろこしなど
その他すいかやきゅうりなども湿の排泄を促しますが、ウリ類は同時に冷やす作用や潤いを補給する働きがあるものも多いので注意が必要です。
また適度な運動で汗をかき、定期的に身体から水分を出すようにすることも湿を溜めないために大切です。
上記のような注意点に気を付けていても、こういった胃腸の働きの弱りからくる様々な症状がなかなか抜けない方には一度鍼灸治療を受けてみるのもお勧めです。
鍼灸治療を行い自律神経のバランスを整えることでこういった症状に改善が見られたケースがいくつもありますので、お気軽にご相談ください(^^)