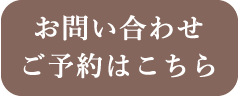梅雨と湿邪
2025/07/08
暑い日が続いていますね。今年は梅雨の時期も全国的に短くされておりますが、関東はまだ明けてはおりません。
梅雨の定義とはなんなのか?というと、日本を含む東アジア地域で特に見られる長期間にわたる雨季の一つで、気象学的には、梅雨は「梅雨前線」と呼ばれる停滞前線の活動の状態とされます。暖かく湿った南寄りの空気と、冷たく乾いた北寄りの空気がぶつかる境界線です。春から初夏にかけて、太平洋高気圧とシベリア高気圧の勢力の変動により、この前線が日本付近に停滞します。この状態が梅雨とされるみたいです。
東洋医学的な観点からいうと、梅雨の湿気は「湿邪(しつじゃ)」と呼ばれ、身体に入り込み悪さをすると考えられています。湿邪は、身体の「脾(ひ)」の消化器系の働きを弱め、湿気を排出しにくくします。症状としては、体の重だるさや倦怠感、頭がぼんやりと重く感じる、むくみやすくなる、食欲不振や消化不良、関節の痛みや関節の重さなどの症状がみられます。
この季節の対策として湿邪を防ぎ、体のバランスを整えるための方法として、食事の工夫もあげられます。例えば、湿気を排出しやすい食材を摂ることです。緑豆、冬瓜、苦瓜、ハト麦、きゅうり、セロリなどは、体内の湿気を取り除く作用があります。また、 脂っこいものや甘いものを多く摂り過ぎると、これらは湿気を増やす原因となるため、控えめにしましょう。
鍼灸は、先にあげた「脾(ひ)」の部分を補う治療もおこなっており、夏バテの予防にもおすすめですので、何かあれば、ご相談ください。