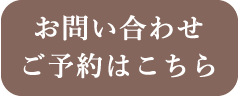耳詰まり感の原因は? 2025年12月13日更新!

こんにちは、冷です。耳鼻科疾患の患者さん耳閉感や詰まり感に悩まれる方がとても多いです。「耳閉感や詰まり感はどこから来た」という質問はしばしばあります、これから説明します。
耳閉感や詰まり感は、耳が圧迫されたような感覚や音がこもる状態を指し、難聴やめまいを伴う場合、内耳の損傷や関連する機能異常が関与している可能性があります。特に突発性難聴や耳管機能の異常、頚部の筋肉や神経の問題、自律神経の乱れが耳閉感・詰まりの原因となることがあります。
1. 内耳の損傷と耳閉感・詰まり
内耳は、音を感知する蝸牛と平衡感覚を司る前庭から成り、聴覚や平衡機能を支える重要な器官です。突発性難聴は、内耳の蝸牛や前庭に急激なダメージを与える疾患で、血流不足や酸素供給の低下、ウイルス感染、ストレスなどが原因と考えられます。内耳の細胞が損傷を受けると、音の伝達が障害され、音がこもる感覚や耳閉感が生じます。この感覚は、耳の中に何かが詰まっているような圧迫感として現れ、感音性難聴や耳鳴り、めまいを伴う場合があります。内耳の損傷は、特に低音域の難聴や音の歪みを引き起こし、耳閉感を増強することがあります。
2. 中耳と内耳の圧力変化
耳は外耳、中耳、内耳の3つの部分で構成され、音の伝達にはこれらの協調が不可欠です。中耳には耳小骨があり、音の振動を内耳に伝えますが、この過程で中耳と内耳の圧力バランスが重要です。突発性難聴の後遺症や耳管機能の低下により、圧力調整がうまくいかなくなることがあります。耳管は中耳と鼻咽腔をつなぐ管で、圧力を調整しますが、機能低下により中耳内の圧力が変化し、耳閉感や詰まり感が生じます。特に、内耳のリンパ液圧の上昇(内リンパ水腫)は、耳閉感や低音域難聴の原因となり、メニエール病でも同様の症状が現れます。
3. 頚部のコリ、頚椎と耳閉感・詰まり
頚部には、頭部や内耳への血流を供給する動脈や神経が集中しています。胸鎖乳突筋や僧帽筋の緊張は、これらの血管や神経を圧迫し、血流を悪化させます。内耳は酸素や栄養に敏感なため、血流不足は内耳機能を低下させ、耳閉感や詰まり感を引き起こします。また、頚部の筋肉の硬直は、内耳への神経信号の伝達を間接的に妨げ、症状を増悪させる可能性があります。
頚椎は、脳から内耳へ信号を伝える神経の通り道です。頚椎の位置異常(例:頚椎症、椎間板ヘルニア)や圧迫は、神経伝達を妨げ、聴覚異常や耳閉感を引き起こします。特に上部頚椎(C1-C2)の問題は、耳に影響を与える神経(例:迷走神経や三叉神経)に影響を及ぼし、耳の圧迫感や詰まり感として現れることがあります。このような神経圧迫は、片側性の症状や耳鳴りを伴う場合が多いです。
4. 自律神経と耳閉感・詰まり
自律神経は、交感神経と副交感神経から成り、血流や耳管の開閉を調整します。ストレス、疲労、睡眠不足による自律神経の乱れは、交感神経の過剰な働きを引き起こし、血管を収縮させます。これにより内耳への血流が減少し、耳閉感や詰まり感が生じます。また、自律神経は耳管の開閉を制御するため、乱れると耳管機能が低下し、中耳の圧力調整がうまくいかなくなり、耳閉感が増強されます。
耳閉感・詰まりを改善する鍼灸アプローチ
当院の鍼灸治療は耳周囲の血流改善と自律神経の調整を中心に行います。
頚部(胸鎖乳突筋、僧帽筋)や耳周囲のツボに鍼や灸を施し、筋緊張を緩和し内耳への血流を促進します。
自律神経の乱れには、交感神経と副交感神経のバランスを整えます。耳管機能低下には、鼻咽腔の炎症を抑えるツボを活用。施術は週2−3回、症状に応じて継続的な治療は効果的です。
追伸
耳閉感・詰まりに難聴やめまい、耳鳴りが伴う場合、突発性難聴や聴神経腫瘍など重篤な疾患の可能性があります。特に、症状が急激に進行する場合や片側性である場合は、速やかに耳鼻咽喉科か鍼灸院を受診してください。自己判断での耳掃除や過度なマッサージは症状を悪化させるリスクがあるため避けましょう。
健康堂 久我山院
西荻窪院
併せて読みたい記事: